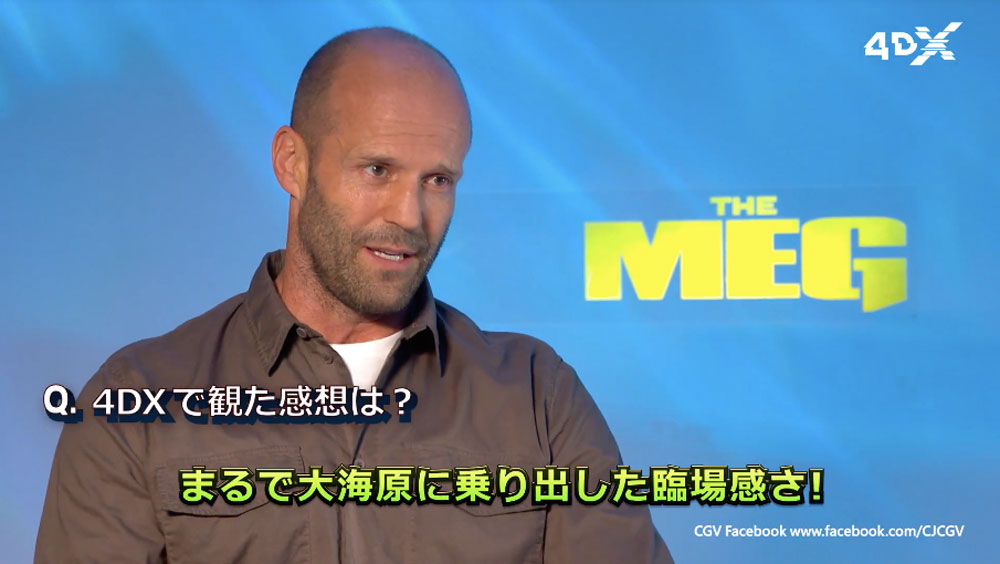毎年1月17日未明から、神戸市の東遊園地*1で阪神大震災の追悼集会が開かれている。
さっき、そこに行っていた。参加するのはたしか3回目。
会場に入った瞬間、なんでまた来てもたんかなと軽く後悔した(後悔するぐらいなら行かなければいいのだけれど、来てしまう。これはもう謎だ)。後悔したのは、参加者より報道関係者の方が多いから。もちろん実際に数をかぞえたなら報道関係者の方が多いということはないはずなのだけれど、とくに5時すぎ、まだ参加者が少ない時間帯では、ほんとうにレポーターとカメラマンとマイクの棒の方が多いように見える。

(これは5時10分ごろに撮ったもの。この写真だとあまり多くは見えないですね)
撮影された映像や写真がメディアに載るときにはうまく切り取られているので、テレビや新聞を介して見る限りはこの報道関係者の多さはほぼ伝わらない。しかし実際に会場にいると違う。各紙各局で同様の映像・写真が用いられるということは、それだけの数の取材ユニットが会場に入っているということである。会場自体、あまり広くない(サッカーコート半面分くらい?)
レポーターや記者はとにかく来場者のコメントが欲しいから、立ち止まっているひとがいたら片っ端から声をかけている。追悼の場に来ている人のさまざまな想いが全国に報道されるのは大切なことだけれど、この「入れ食い」状態はあまり好ましいものに思えない。祈りの場には静けさと穏やかさが必要だとおもう。レポーター、肩に担がれた大きなカメラ、旗竿のようなマイクは、この場所では端的に言って異物だ。*2 来場者のまなざしやたたずまいとは異質な挙動や語り口や時間を差し込んでいる。
わたしが代弁することは決して正しいことではないけれど、遺族と呼ばれる立場のひとびとや亡くなった方に近しいひとびとは、カメラや記者に自分の体験や感情を語ることを好まない/差し控える/躊躇することが多い(もちろんケースバイケースであって、語ることが必要であると感じることや、語ることを使命と決意するひともいる)。「あの会場に行くと、すぐに記者に捕まる」というイメージを与えてはいないか。もしそうだとすると、何のためにかれら報道関係者は会場に来ているのだろう。
来場者は基本的にじっと立ち止まっている。あるいはしゃがみこんでいる。竹灯篭のロウソクに火をつけると、あとはあまりすることがない。ところが報道のひとは基本的にうろうろしている。この静と動が混ぜ込まれることで、会場全体が独特の妙な雰囲気をもつ。個人的には、静か動かどちらかに寄せてくれると居やすいのだけれど…。
なおコツ(?)を書いておくと、北側から会場に入ってすぐのゾーンは報道関係者が重点的に待ち構えていて、ここで立ち止まってしまうと即取材される。会場の南側に抜けると「安全ゾーン(?)」になっていて、ここはあまりレポーターや記者は声をかけてこない。ただしこのゾーンには市長がいたりして、一帯がなんだか妙な雰囲気になることがある。
最後に、すごく悲しかったことがある。追悼集会のプログラムはとてもシンプルで、5時46分に黙祷が行われたあと、「遺族代表のことば」と「市長のことば」が順に語られる。遺族代表の方が実際に会場で話を始めるところにわたしは初めて立ち会ったのだけれど、けっこう、みんな、聞いていない。ざわざわうろうろしている。これは衝撃だった。
会場にはいろいろな立場のひとが来ているけれど、やはり、亡くなったひとびと当人と、その家族は、この場所でもっとも大切なひとであるはず。けれども、その遺族がまさに自分自身のことばで語っている場面で、会場全体がそれをスルーしているように感じた。だれも立ち止まっていない。聞いていない。これがすごくすごく悲しかった。
多少関係するエントリ: